|1 会長挨拶/祝辞|2 活動の記録|3 特集・さまざまな人生(1)|4 特集・さまざまな人生(2)|5 資料|
 機関誌「奏苑」 第6号(1994.07.09発行)《1》
機関誌「奏苑」 第6号(1994.07.09発行)《1》
岩高吹奏楽部定期演奏会30回・吹奏楽コンクール東北大会出場記念 − 1 of 5 −
|
1 会長挨拶/祝辞
2 活動の記録
5 資料
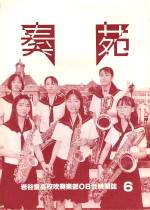 |
四半世紀を越えてOB会会長 高野正浩今回で、奏苑は第六号になる。会員の数は四〇〇名を超えた。創立以来二十六年。今日まで続いて来たのは、会員一人一人の思い出の中で、先輩、後輩の別無く共有した三年間があったからだと思う。たしかにそれは他の部にも言えるだろう。しかし、吹奏楽部についてはちょっと違うと思う。各部共に地区大会、県大会に向けて練習を行っている。それは吹奏楽部も同じではあるが、一つの曲を仕上げると言うさらに細かい目標がある。 その結果が県大会、東北大会出場である。他の部とは違う、きめの細かいチームワークがあった為に、今日まで続けられたのである。 定期演奏会は第三十回をむかえる。それを記念して、OB会のオリジナル曲を作ることにした。たぶんみなさんが、この文章を読む時は、すでに発表されていることと思う。東北大会初出場の現役達に、OB会のすばらしさを教えてあげようと思う。 昔とちがい、OBとのコミュニケーションの少ない今、OB会のすばらしさを教える事も なかなかむずかしくなってきている。現に、OB会があっても、若手が出席してくれない。OB会を三十周年、四十周年と続けて行くにはどうしたらいいか。若手を呼び込むにはどうしたらいいかを、本気で考えなくてはならない。以前、仙台支部で出席していただいた、女性の先輩に「子供が大きくなって、手がはなれたので、昔を思い出しに来ました。」と言われたが、若手が歳をとり、そういう状況になった時、OB会というきっかけがあれば、なつかしい思い出を語り合えるのだと思う。OB会は、役員だけが運営するのではなく、みなさん一人一人がいて、はじめて成り立っていると言う事を、忘れないでほしい。 最後になりましたが、昨年の吹奏楽コンクール東北大会初出場の際には、皆様方には、たくさんの寄付をいただき、誠に有り難うございました。現役の生徒達に、OB会の存在をあらためて感じさせる事が出来たと思います。 これからも現役の後援とOB会員相互の交流を深めるべく、活動を続けて行きますので、今後共、ご協力をお願い致します。 奏苑の発刊を祝して校長 本間良樹岩高吹奏楽部OB会創立二十六周年と機関誌「奏苑」第六号発刊を心からお祝い申し上げます。 常日頃、本校吹奏楽部活動に物心両面にわたりご支援・ご指導をいただいておりますことに感謝申しあげます。おかげさまで昨年度は全日本吹奏楽コンクール岩手県大会で最優秀賞を、そして東北大会では銅賞を獲得するという輝かしい実績を残すことができました。 今年度も、いっそう盛り上がりをみせ、各種大会に備え、また七月の定期演奏会を成功させるべく、顧問・部員一丸となって練習に励み、努力いたしております。 数学者広中平祐氏は「ある時期に音楽に凝った、楽器に凝ったということが、ひとつのその人の情操、あるいは美感みたいなものをつくっている」とある著書で述べ、数学をやる上でもそういう美感みたいなものが確かに働いている、と述懐しております。 音楽の音色というものは、人の心から生まれてくるもの(礼節)です。OB会の皆さまがそうでありますように、部員にとっても高校時代に、ひたすら美しい音を作り、他と(を)和することに熱中した体験は何にも代え難い財産になることでありましょう。 孔子は、 人生の勉強の最終段階は「音楽を楽しみ、心をやわらげ、情操を涵養することである」と弟子たちに教えております。 音楽には全くの門外漢である私は、皆さまをとても羨ましく思います。 所感の一端を述べ、お礼とお祝いのあいさつといたします。 奏苑第六号発刊を祝う同窓会長 小野田徹朗奏苑第六号発刊おめでとうございます。 雨の日曜日、江刺郵便局の高橋さんがわざわざ届けてくれた第五号。OBの皆さんの沢山の原稿がのっている。 どなたの文章にも、熱がこもっていて、心を打つものがあります。 そこには、岩高で過ごした部活の想い出が数々綴られています。 どこの学校にも、卒業生の集まりで良く歌われる歌があります。それは、校歌であったり、応援歌であったり、寮歌であったり……。色々ですが、仲間と一緒に歌っている時は、先輩も後輩もなく、自分の年齢も忘れ、あたかも青春に最中にある様な感じがして来ます。 岩高讃歌もきっと、この様に歌いつがれて行くのだろうと思います。 卒業式の時、ブラスバンドの伴奏で歌う諸君の双眸は光り輝き、頬は紅潮し、心は熱く燃えているのがよくわかります。熱気が伝わって来る。そして、かって過ごした北国の想い出と重なってくる。 夜空を焦がす炎、寮歌、応援団の太鼓、ファイヤーストーム……誰かが校歌を歌う。 永遠の幸 朽ちざる誉 つねに我等がうえにあれ よるひる育て あけくれ教え 人となしし我庭に イザイザ うちつれて 進むは今ぞ 豊平の川 尽くせぬながれ 友たれ永く友たれ ……… 今日まで皆で培って来た吹奏楽部の素晴らしい伝統を、更にはぐくみ育て、岩谷堂高校の実質を一層高めて頂きたいと願うものであります。 OB会とOBの皆様のますますの御健勝とご活躍をお祈りする次第です。 奏苑第六号発行に寄せて顧問 小川浩子/西村隆一/平野美知子岩高吹奏楽部OB会創立二十六周年、さらに奏苑第六号の発行おめでとうございます。 岩高も今年七十六周年目を迎え、吹奏楽部も大きく躍進しようとしております。 定演も今年で三十回目を迎えることが出来、さらに去年は東北大会に出場することが出来ました。これもひとえに、OB会の皆様をはじめとする多くの方々の温かいご支援の賜物と心より感謝いたしております。 先日、五月三日には恒例の江刺甚句祭りでの発表を終え、現在は定演、そしてコンクールに向け、及川孝さんのご指導のもとに毎日練習に励んでおります。母校においでの節は、アドバイス等をお願いしたいと思います。 最後に、OB会の皆様の尚一層のご支援をお願いすると共にOB会の発展をお祈り致します。 なお、この度は楽器を寄贈していただき、心からお礼申し上げます。 更なる向上を目指して部長 及川千里岩高吹奏楽部OB会設立二十六周年おめでとうございます。合わせて、今年度の定期演奏会も三十回目を迎えることとなりました。このような素晴らしい伝統を持つ吹奏楽部に、今の私たちがあることを、大変うれしく思います。 現在の部員数は女子四十五名で、あまり多いとは言えない人数で成り立ち、今は定期演奏会、吹奏楽コンクールに向けて頑張っています。 しかし、この頃部内に活気が見られず、多少だらだらしている感じもあります。 「他人まかせ」で自主性が見られない傾向があり、このままでは良い演奏は出来ません。 昨年は、吹奏楽コンクール東北大会出場という夢のような結果でした。今年は更に上を目指していきたいと思っています。しかし、このままでは去年を越える演奏をするのは難しいことでしょう。この「他人まかせ」を解消し、部員一人ひとりが意識を高く持って練習に臨みたいと思います。 今、私たちは七月十日に行われる定期演奏会、八月初めの吹奏楽コンクールに向けて、練習を重ねています。進路のことやいろいろなことで悩んでいたりもしますが、まず定期演奏会を大成功に終わらせ、コンクール上位を目指して頑張りたいと思います。 OBの皆様には、いろいろとお世話になると思いますが、よろしくお願いします。 最後に再び、OB会設立二十六周年おめでとうございます。 |
